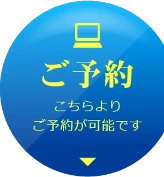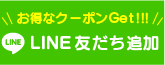和光市デンタルオフィス
症例・ブログ
CASE・BLOG
【脱マスクにむけて!】変色歯・着色歯はどうやってきれいにするの??
こんにちは!和光市デンタオフィスです!
だんだん暖かさから暑さに代わり、初夏を感じる日もでてきましたね!
今年は「脱マスク」がさらに加速して、その準備に取り掛かる方が増えてきた印象です😊
歯並びや虫歯治療はもちろんですが、その中でも特に多いのが「歯の変色・着色」のお悩みです。
いくらお化粧や服装で身だしなみを整えても、笑った時に前歯が変色していたり、黄ばんでいたり、何か適合の悪い被せ物が入っていたり、銀歯が見えたりすると、どこか痛ましい印象を与えてしまい、他の努力が水の泡になってしまうそうです。
言われてみれば、そういった口元の美しさは自然と目が行ってしまうな・・・と同感しました。
ただ、近年「審美歯科」という言葉が広まり、気軽に「歯を白くできる」というメニューや商品が増えています。
またその中にも高額なものがあり、「お金をかければきれいになるだろう」と思い込んでしまう人々もいるので、本当にその患者様の適応なのか?ということがないがしろにされている印象があります。
大切なのは、自分は今どういう状況で、どういった処置が必要なのか?を知ったうえで判断することです。
一番は歯医者さんで相談することですが、少しでも歯医者さんに相談してみようというきっかけになったり、相談する上で知識を身に着けていただくことも大切なので、この記事が少しでも皆さんのお役に立てたらうれしいです。
【外因性因子と内因性因子】
歯の色の変化には、①歯の表面への沈着物②歯の表面、あるいは歯の硬組織内の着色③歯の色調変化による変色この3つがあります。
これらの原因には患者さんの生活習慣に由来するもの、医療の結果によって生じるいわゆる医原性のもの、歯の生理的な変化によるものなどがあります。
この記事では、生体外由来の外因性因子・生体内由来の内因性因子に分けて解説させていただきます。
《外因性因子》
①歯の表面の沈着・着色
歯磨きがしにくい歯茎の際、歯と歯の間、噛む面のいわゆる不潔域に着色の沈着は起こりやすいです。
付着物の種類としては、
・乳白色から黄色の歯垢(以下プラーク)
・淡褐色から緑褐色の歯茎の中に入り込んだ歯石(以下縁下歯石)
・茶褐色から黒褐色の食べ物による外来色素
・グルコン酸クロルヘキシジンのうがい薬による外来色素(深緑のもの等)
などが代表例として挙げられます。
これらは、食生活の改善、定期的なクリーニング、日々のブラッシングで改善されますし、予防できます。

クリーニングできれいに。
また、今は使用されることはありませんが、以前、知覚過敏症や虫歯予防・進行抑制の治療に使われていた金属塩(フッ化ジアンミン銀、硝酸銀)を歯面に塗布すると歯が黒色に変色しますので、過去にそういった処置を受けられた方は歯にそういった跡が見られます。
②虫歯
虫歯が原因となる歯の色の変色には、初期むし歯の段階で、エナメル質という表層の組織のミネラルが漏洩したことによる「脱灰」という症状によるもので、白色および褐色へ変色します。
またさらに虫歯が進行すると、象牙質という内層の組織が黄白色から茶褐色病変があり、これはさらに慢性化すると黒褐色へと変化します。
これらは、むし歯の菌が産生する有機物質や、飲食物による外来色素が弱った歯質に浸透するためとかんがえられています。
エナメル質初期のむし歯の脱灰に関しては、日常の歯磨きでしっかりプラークを除去し、フッ化物の局所応用によりむし歯の進行を抑制し、再度ミネラルを取り戻す(再石灰化)治療が優先されます。
もう少し進行したむし歯だと、白いプラスチックの詰め物を詰めたりして修復処置を行います。
③修復物由来の変色・着色
修復物(治療で詰めた材料)由来の変色・着色には修復材料自体の変化によるものと、修復物周囲の歯質の変化によるものの2つに分けられます。
修復材料自体の変化によるものは、主に材料の経時的劣化に起因するものです。
修復材料の多くはプラスチック材料のものが多く、タッパーのように変色したり、粗造面に着色が付いたりします。
劣化が材料深部にまで及んでいる場合は、一度その材料を除去し、新しく詰めなおします。範囲が広ければ、型取りをして歯の形にあった詰め物をするのもいいでしょう。
修復物周囲の変化としては、2次むし歯によるものや、金属の詰め物などから溶け出した金属イオンによる周囲象牙質の黒変があります。
いずれも再度変色してるところを削り、再治療が必要です。
また、セラミックなどの部分的な詰め物をしている方は、被せ物はずっときれいでも天然歯が加齢による変色で、色調の不一致が生じることもあります。
一番奥歯などは難しいですが、手前の歯ならホワイトニングをして、天然歯の色調を合わせるのも方法の一つです。
④根管治療薬剤による変色
歯の神経まで到達してしまった歯は、神経を取る治療をしなければいけませんが、少し前の時代の治療の際に使う薬剤の影響で、歯が黒変してしまうことがありました。
今では使われていませんが、過去にそういった治療を受けてこられた方は、そういった変色が見られます。
変色してしまった歯質を削り、被せ物をする治療が必要になります。
《内因性因子》

どうやって白くする?
①加齢変化
歯の色調は、歯の石灰化(ミネラルの密度の濃さ)に左右され、石灰化の良い歯は黄色、石灰化の良くない歯は乳白色です。
なので、子供のころの乳歯はまだ未熟な歯なので大人の歯に比べて白く見えますし、年を重ねると、石灰化が進み、どんどん丈夫になるのと同時に黄色くなっていきます。
一般的にはホワイトニングで歯を漂泊して白さを取り戻します。
②歯の神経の病変
歯をぶつけたりして歯の神経が壊死してしまったときに、出血が組織内に入り込み、歯を変色させてしまいます。
歯質が十分残っていれば歯の根っこをきれいにし、ブリーチングを行います。
しかし、歯質が半分以上残っていない場合は、被せ物が必要になります。
③薬物による変色
ある特定の薬物を投与すると、歯が変色してしまうことが分かっています。
その薬物とはテトラサイクリン系抗生物質です。
テトラサイクリン系抗生物質とは、昭和40年代に最も頻用された抗生物質で、子供時代に投与されていた影響で、成人になり、永久歯の変色につながってしまっています。
当時は、子供や妊婦への投与は注意勧告されていたとのことですが、この変色の実態で以前子供に対しても投与されていたことが明らかになりました。
このテトラサイクリン歯には、軽度であればホワイトニング、重度であれば被せ物やラミネートべニアの治療をします。
④歯の形成不全
歯の形成不全とは、成長過程で何らかの問題があり、歯がしっかり育つことが出来なかったことをいいます。
この形成不全には、局所的要素と全身的要素があります。
局所的要素とは、乳歯の打撲・乳歯を抜歯するときに加わった刺激・乳歯の歯の根っこの病気などの影響により、後から生えてくる永久歯が石灰化不全となり、チョークのような白い模様や褐色斑が生じることを言います。
見た目は前述で述べた虫歯による脱灰に似ていますが、汚れの付き具合や白斑が現れる場所で、虫歯によるものか、形成不全によるものかを判断します。
白斑部分を削って上からプラスチックを詰めたり、場合によっては被せたりします。
また、エナメル質形成不全の方はホワイトニングが出来ないので、注意が必要です。
全身的要素とは、幼少期にフッ素を過剰に取り込むことによっておこる歯牙フッ素症、幼少期に麻疹・風疹・水痘など、長期にわたり高熱を発症する疾患にかかる際に、エナメル質が変色する熱誠疾患によるもの、遺伝のもの、先天性ポルフィリン症やカルシウム代謝異常などの代謝異常によるもの、幼少期のビタミンD不足による栄養障害などがあります。
これらは、ラミネートべニア修復歯やコンポジットレジン修復で治していきます。
いかがでしたか?変色・着色と言ってもこれだけ種類があるので、その都度対応も変わってきます。
一つ言えることは、どんな変色・着色にも必ず改善方法はあるので、あきらめずにまずは相談してみることが大切ですね。

誰でも綺麗な歯に
カテゴリ
- 虫歯 (29)
- 歯周病 (16)
- 小児歯科 (3)
- 矯正歯科 (16)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (2)
- 顎関節症 (2)
- 噛み合わせ異常 (5)
- マイクロエンド (2)
- セラミック (24)
- インプラント (16)
- 小児矯正 (7)
- マウスピース矯正 (28)
- ワイヤー矯正 (21)
- 部分矯正 (18)
- ホワイトニング (21)
- デンタルエステ (30)
- デンタルIQ (83)
- スタッフブログ (68)
アーカイブ
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)