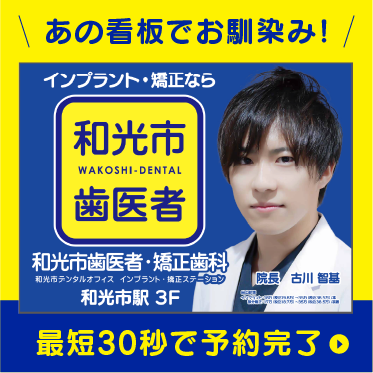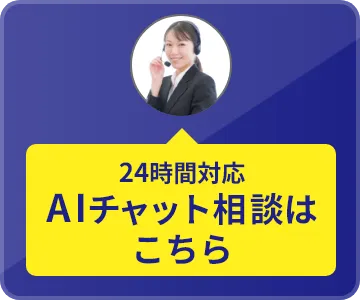和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
子どもの歯並びを守るためにできること
前回の記事では、「なぜ子どもの歯並びが悪くなってしまうのか?」という原因についてお話ししました。
口呼吸や指しゃぶり、やわらかい食べ物ばかりの食生活など、普段の生活習慣が歯並びに大きく影響していることをお伝えしましたね。
では実際に、どうすれば歯並びが悪くならないようにできるのでしょうか?
今回は「ご家庭でできる工夫」と「歯科医院で受けられるサポート」の両面から、具体的な予防の方法をご紹介します。
ご家庭でできる予防の工夫

子どもの歯並びは、実は遺伝だけで決まるものではありません。日常の習慣や体の使い方が大きく影響していることが分かっています。ご家庭で少し意識を変えるだけでも、将来の歯並びに良い影響を与えることができます。ここでは、すぐに始められる予防の工夫をご紹介します。
正しい姿勢・呼吸習慣(口を閉じて鼻で呼吸)
子どもの歯並びを守るうえで、とても大切なのが「口を閉じて鼻で呼吸する習慣」です。
お口がぽかんと開いている状態(口呼吸)が続くと、舌の位置が低くなり、本来は上あごを内側から押し広げて支えるはずの舌の力が働かなくなってしまいます。その結果、上あごの横幅が狭くなり、歯が並ぶためのスペースが不足し、ガタガタの歯並び(叢生)につながりやすくなります。
さらに口呼吸は、歯並びだけでなくお口の健康全体に悪影響を及ぼします。お口が常に乾燥するため、むし歯や歯肉炎のリスクが高まり、口臭の原因にもなります。また鼻呼吸には「空気を温めて湿らせ、異物を除去する」というフィルター機能があるため、鼻呼吸ができない子は風邪やアレルギー、感染症にもかかりやすいといわれています。
呼吸の仕方と姿勢も密接に関係しています。姿勢が悪く猫背になると、胸やお腹が圧迫されて呼吸が浅くなり、自然と口呼吸になりやすくなります。特に、スマホやゲームなどで長時間前かがみになる習慣は要注意です。正しい姿勢で座り、背筋を伸ばすことは、鼻呼吸を習慣づけるための大切な基盤になります。
ご家庭でできる工夫としては、まず「今この瞬間、口が開いていないかな?」と日常の中で意識して観察することです。テレビを見ているとき、集中して絵を描いているとき、寝ているときなどに口が開いているようであれば、口呼吸のサインかもしれません。その場合は「お口を閉じて鼻でスースーしようね」と優しく声をかけてあげましょう。
鼻づまりやアレルギーなどで鼻呼吸が難しい場合もありますので、そうしたときは耳鼻科や歯科に相談し、原因を取り除いてあげることも大切です。
噛む力を育てる食習慣
子どもの歯並びを守るうえで「よく噛むこと」はとても大切です。噛む回数が少なかったり、やわらかい食べ物ばかりを食べていると、顎の骨や筋肉がしっかり発達せず、歯がきれいに並ぶためのスペースが足りなくなってしまいます。つまり「顎の育ち」が不十分になることで、歯並びの乱れにつながるんですね。
昔に比べると、現代の食事はどうしてもやわらかいものが多くなりがちです。ハンバーグやパスタ、パンなどは子どもも食べやすいですが、噛む回数は少なく済んでしまいます。そこで意識して取り入れていただきたいのが、しっかり噛まないと飲み込めない食材です。たとえば、にんじんや大根のスティック、きゅうりなどの生野菜、干し芋やスルメ、りんごなどの果物は噛むトレーニングにぴったりです。
噛むことには、顎の発達以外にもいいことがたくさんあります。噛む刺激で脳が活性化し、集中力が高まることもわかっていますし、唾液がよく出ることでむし歯予防にもつながります。さらに、食べすぎを防いで肥満の予防にも役立つんです。
ご家庭でできる工夫としては、食事中に「30回噛んでみよう!」とゲーム感覚で声をかけたり、歯ごたえのある食材を一品加えてみたりするのがおすすめです。また、テレビやスマホを見ながらの“ながら食べ”だと噛む回数が減ってしまうので、「食べるときは食べることに集中する」という習慣づけも大切です。
噛む力を育てることは、将来の歯並びを整えるための土台づくりです。毎日の食事の中で少しずつ意識するだけで、大きな差が生まれますので、ぜひ楽しみながら取り入れてみてくださいね。
悪習癖の改善(指しゃぶり・頬杖・うつぶせ寝など)
子どもの歯並びに影響を与える「お口の癖(口腔習癖)」は、実はご家庭で気づきやすいポイントのひとつです。代表的なのが指しゃぶりや頬杖、うつぶせ寝といった習慣。大人からすると「小さい子どもならよくあること」と思われがちですが、続けていると歯並びや顎の成長に大きな影響を与えてしまいます。
まず指しゃぶり。乳幼児期には安心感を得る行動として自然なものですが、3歳を過ぎても習慣が続くと注意が必要です。指が前歯を押し続けることで前歯が前に出たり、上下の前歯が噛み合わない「開咬(かいこう)」になったりすることがあります。寝ている間やテレビを見ているときに無意識で指をくわえていることも多いので、さりげなく声をかけて気づかせてあげることが大切です。完全にやめさせるのではなく、「一緒にやめていこうね」という姿勢で取り組むとお子さんも前向きになれます。
次に頬杖。勉強中やテレビを見ているときに片方の頬を押し続けると、歯列や顎に左右差が出てしまうことがあります。特に成長期は顎の骨がやわらかいので、力が加わり続けると歪みやかみ合わせのズレにつながりやすいのです。「姿勢を正そうね」と優しく声をかけるだけでも改善につながります。
また、うつぶせ寝や横向き寝の習慣も要注意です。寝ている時間は長いため、頬や顎にかかる圧力の影響は意外と大きく、歯並びや顎の発育に関わってきます。仰向け寝を基本に、枕や寝具を工夫して寝やすい環境を整えてあげるのも一つの方法です。
このような「ちょっとした癖」は、子ども自身が気づかないうちに繰り返していることが多いため、まずはご家族が観察してあげることが大切です。そして、責めたり強制したりするのではなく、少しずつ習慣を変えていけるようにサポートしてあげましょう。
歯科医院でのチェックとサポート

定期検診でのかみ合わせチェック
歯並びやかみ合わせの乱れは、ある日突然起こるわけではなく、少しずつ積み重なって表れてきます。そのため、歯科医院での定期検診は「むし歯予防」だけでなく「歯並びの早期発見」のためにもとても大切です。
特に乳歯から永久歯に生え変わる時期は、歯の大きさと顎の成長のバランスがとれているかどうかをチェックする必要があります。例えば「前歯がかみ合わない」「奥歯がずれてかんでいる」「歯が重なって生えてきている」など、小さなサインを見逃さずに確認できるのが歯科検診の強みです。
歯科医師や歯科衛生士は、歯の並び方だけでなく「舌の動き」「口呼吸の有無」「顎の成長具合」なども含めてトータルにチェックします。これらはご家庭ではなかなか気づきにくいポイントですが、専門家が見ることで「今は経過観察でよいのか」「早めに対応した方がよいのか」の判断ができるのです。
また、歯並びの乱れは見た目だけでなく、しっかり噛めない、発音がしにくい、顎関節に負担がかかるなど、将来的な機能面の問題にもつながる可能性があります。定期的なチェックはそうしたリスクを未然に防ぐための第一歩といえるでしょう。
ご家庭では「そろそろ永久歯が生えてきたな」「最近よく口が開いている気がする」など、ちょっとした変化に気づいたときが受診のタイミングです。定期検診を習慣にしておくと、安心して成長を見守ることができますよ。
MFT(口腔筋機能療法)などの早期介入
歯並びの乱れは、歯そのものの問題だけではなく「お口の周りの筋肉の使い方」と深く関わっています。そこで注目されているのが MFT(口腔筋機能療法) です。これは、舌・唇・頬などのお口の筋肉をトレーニングすることで、正しい使い方を身につけ、歯並びやかみ合わせの乱れを予防・改善していく方法です。
例えば、舌がいつも下に落ちている子は、上あごが広がらず歯が並ぶスペースが足りなくなりやすいですし、口呼吸の癖がある子は唇や頬の筋肉が弱く、前歯が前に出やすくなります。MFTでは、こうした筋肉のバランスを整え、「舌を正しい位置(上あごの天井部分)に置く」「鼻で呼吸する」「唇を自然に閉じる」といった習慣を身につけられるようにトレーニングしていきます。
トレーニングといっても、難しいものではありません。例えば「舌でスポットと呼ばれる位置に舌先を置く練習」「口を閉じて鼻呼吸を意識する練習」「ストローを使って吸う練習」など、遊び感覚でできる内容が多いのが特徴です。毎日の生活の中で少しずつ繰り返すことで、無意識の癖が自然と良い方向へ変わっていきます。
歯並びに影響する習慣は、子どもの成長とともに定着してしまうことが多いため、早めに気づいて改善していくことがとても大切です。MFTは「歯並びが悪くなってから矯正で治す」のではなく、「歯並びが乱れにくい環境を整える」ためのアプローチともいえます。
ご家庭では難しい部分もありますので、歯科医院での指導を受けながら取り組むのがおすすめです。専門的なサポートを受けることで、トレーニングの効果をしっかり実感できるはずです。
必要に応じた小児矯正(床矯正・マウスピース型矯正など)
子どもの歯並びに乱れが見られたとき、「すぐに矯正が必要なのかな?」と心配される保護者の方は少なくありません。実際には、すぐに治療を始める必要があるケースもあれば、成長を観察しながら様子を見るケースもあります。大切なのは「その子の成長段階に合った方法を選ぶこと」です。
小児矯正にはいくつか種類がありますが、代表的なのが 床矯正(しょうきょうせい) と マウスピース型矯正 です。
床矯正は、取り外し式の装置を使って顎を少しずつ広げ、歯が並ぶためのスペースを作ってあげる方法です。永久歯がきれいに生えてくる“場所”を確保するイメージで、歯を無理に動かすのではなく、顎の成長をサポートするのが目的です。比較的低学年の子どもに向いており、装置を外して食事や歯磨きができるので衛生面でも安心です。
一方、マウスピース型矯正は、透明のマウスピースを使って少しずつ歯や顎の位置を整えていく方法です。見た目が目立ちにくく、装着感も比較的やさしいため、子どもにとって負担が少ないのが特徴です。口腔筋機能療法(MFT)と併用することで、歯並びの改善だけでなく、お口の正しい使い方を身につけることにもつながります。
これらの治療は「将来、本格的な矯正をしなくても済むように」あるいは「矯正が必要になっても負担を減らせるように」といった予防的な役割を持っています。つまり、小児矯正は“今すぐきれいな歯並びを作るため”というより、“将来の成長を見据えて土台を整えるため”に行うことが多いのです。
保護者の方には「矯正を早く始めなければ手遅れになる」というプレッシャーを感じる必要はありません。大切なのは、定期的に歯科医院でチェックを受けて、必要なタイミングで必要なサポートを受けることです。それだけで、子どもの歯並びは安心して見守ることができますよ。
お子さんの歯並びに対して不安に思ってる親御さんへ

お子さんの歯並びを心配して、「すぐに矯正を始めた方がいいのでは?」と不安になる親御さんも少なくありません。ですが、まず大切なのは 焦らず、成長を見守りながら定期的に歯科で確認を受けること です。
子どもの歯やあごの発達は一人ひとりスピードが違います。たとえば今少し歯並びがガタついて見えても、成長とともに自然に改善されるケースもあれば、反対に放っておくと将来大きなズレにつながる場合もあります。だからこそ、歯科医院での定期的なチェックが欠かせないのです。
また、日々の生活習慣が歯並びに直結するということも忘れてはいけません。
「鼻で呼吸をする」「よく噛んで食べる」「頬杖や指しゃぶりをしない」など、ちょっとした意識の積み重ねが、将来のお口の健康を左右します。
親御さんが正しい知識を持ち、日常生活で見守ってあげることこそが、お子さんにとって何よりのサポートです。矯正治療が必要かどうかの判断も、歯科医院と一緒に考えれば大丈夫。“小さいころの習慣づくりが、一生ものの歯並びと健康を守る” という気持ちで、お子さんの成長を応援していただけたらと思います。
まとめ
子どもの歯並びを守るためには、家庭でのちょっとした工夫と歯科での定期的なチェック、この両方が欠かせません。前回の記事では「歯並びが悪くなる原因」についてお伝えしましたが、今回はその原因に対してご家庭でできる予防策や、歯科でのサポート方法を具体的にご紹介しました。
「鼻で呼吸する」「よく噛む」「悪習癖を減らす」といった日常の習慣づくりや、定期検診でのかみ合わせチェック、MFT(口腔筋機能療法)や小児矯正といった専門的なサポートを組み合わせることで、将来の歯並びのリスクを大きく減らすことができます。
大切なのは、親御さんが焦らず、子どもの成長を見守りながら必要なタイミングでサポートすることです。小さいころからの生活習慣や日々の観察が、お子さんの一生の歯の健康につながります。
もし「子どもの歯並びが気になる」「どのタイミングで歯科に相談すればいいかわからない」と感じたら、ぜひ【和光市歯医者・矯正歯科】和光市デンタルオフィスにご相談ください。当院では、お子さん一人ひとりの成長に合わせた丁寧なチェックと生活習慣改善のアドバイス、必要に応じた小児矯正まで、安心して受けていただけるサポート体制を整えています。日々のケアの延長として、専門家と一緒にお子さんの歯並びを守っていきましょう。
カテゴリ
- 虫歯 (53)
- 歯周病 (38)
- 小児歯科 (17)
- 矯正歯科 (30)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (5)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (20)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (19)
- 小児矯正 (19)
- マウスピース矯正 (40)
- ワイヤー矯正 (29)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (31)
- デンタルエステ (42)
- デンタルIQ (119)
- スタッフブログ (116)
アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (5)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)