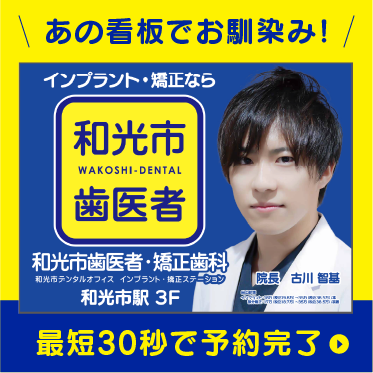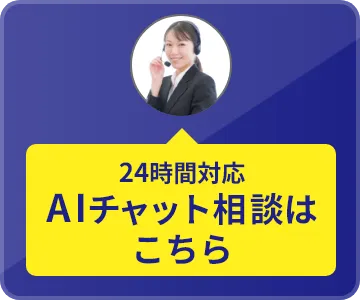和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
マウスピース矯正で治せる歯並び
今大注目のマウスピース矯正

「歯並びをきれいにしたいけれど、ワイヤー矯正は目立つのが気になる…」
そんな方に近年人気を集めているのが マウスピース矯正 です。透明で目立ちにくい見た目や、取り外しができる利便性から、幅広い年代の方に選ばれています。
マウスピース矯正とは、薄くて透明なプラスチック製のマウスピース(アライナー)を段階的に交換しながら歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。コンピューターで歯の動きをシミュレーションし、数十枚単位のマウスピースを順番に装着していくことで、理想的な歯並びへと導いていきます。従来のワイヤー矯正が「ブラケットとワイヤーで力を加えて歯を動かす」のに対し、マウスピース矯正は「アライナーを少しずつ形を変えていくことで歯を誘導する」という点が大きな違いです。
最大のメリットは、装置がほとんど目立たないことと、食事や歯磨きの際に取り外せるため、口腔内を清潔に保ちやすいことです。また、金属を使用しないため金属アレルギーの心配がない点も安心材料といえるでしょう。さらに近年ではデジタルスキャナーやAI技術の進歩により、より正確で効率的な治療計画が立てられるようになっています。
ただし、マウスピース矯正には得意・不得意があり、すべての歯並びに対応できるわけではありません。比較的「軽度~中等度の歯並びの乱れ」には効果的ですが、骨格的なズレや重度の歯列不正に対しては限界があります。そのため、「マウスピース矯正で治せる歯並びと、治せない歯並び」を知っておくことが、治療を考えるうえでとても大切なのです。
今回はその中でもまず、「マウスピース矯正で治せる歯並び」について、具体的な症例を挙げながらご紹介していきます。
治せる歯並びの具体例

軽度~中等度の叢生(歯のデコボコ)歯の移動スペースがある程度確保できる場合。
歯並びの相談でとても多いのが「叢生(そうせい)」、いわゆる歯のデコボコです。見た目で「前歯がガタガタしている」「八重歯が出てきてしまった」という状態がこれに当たります。叢生は見た目だけの問題と思われがちですが、実は歯磨きがしづらくなり、むし歯や歯周病のリスクを高める大きな要因にもなります。
叢生が起こる一番の理由は、顎の大きさと歯の大きさのアンバランスです。顎の骨が小さめなのに歯のサイズがしっかり大きいと、きれいに収まるスペースが足りず、前後にずれたり斜めにねじれたりして生えてきます。これは生まれ持った骨格の影響もありますが、子どものころの習慣(やわらかい食べ物ばかりで顎が発達しにくい、指しゃぶりや口呼吸など)も関わっていると言われています。つまり、叢生は「体のつくり」と「生活習慣」の両方の影響で出てくるのです。
さて、この叢生に対してマウスピース矯正がどこまで力を発揮できるかですが、特に 軽度から中等度 のケースであればとても相性が良い治療です。マウスピースは段階的に少しずつ形を変えながら歯に力をかけていきます。例えば、内側にねじれてしまった前歯を外に回転させたり、歯列のアーチをほんの少し広げてスペースを作ったりといった細かい調整が可能です。近年では3Dシミュレーションを用いて「どの歯を何ミリ、どの方向に動かすのか」をあらかじめ計画できるので、治療のゴールが目で見える形で確認できるのも安心につながります。
ただし、叢生が重度になると話は変わってきます。この場合、顎の中に収めるためのスペースを作るには歯を抜く必要があったり、ワイヤー矯正と組み合わせないと難しかったりします。つまり「どの程度の叢生か」を正しく診断することが、治療法を決めるうえで非常に大事なんです。
もう一つ忘れてはいけないのは、叢生を整えることで見た目がきれいになるだけではなく、お口の健康にも大きなメリットがあるということです。デコボコした部分は歯ブラシの毛先が届きにくく、プラークが残りやすい場所になります。そのため、むし歯や歯ぐきの炎症を繰り返しやすいのです。歯並びをきれいに整えておくことは、将来的に「自分の歯を長く守る」ことにもつながります。
ですから、「前歯がちょっと重なってるだけだし…」と軽く考えずに、もし気になるようであれば一度専門家に相談してみるのがおすすめです。マウスピース矯正で対応できる範囲なのか、それとも他の方法が適しているのか、きちんと診てもらうことで安心できますし、治療を始めるかどうかの判断もしやすくなります。
すきっ歯(空隙歯列)
「すきっ歯」と聞くと、なんとなく見た目のイメージを思い浮かべる方が多いかと思います。前歯の真ん中にすき間があるケースが代表的ですよね。専門用語では「空隙歯列(くうげきしれつ)」と呼びますが、これは歯と歯の間に隙間がある歯並びのことを指します。
実はこの「すきっ歯」にはいくつか原因があります。
代表的なのは、
- 顎の大きさに対して歯が小さい
- 歯の本数が先天的に少ない(先天性欠如歯)
- 舌のクセや、口呼吸の影響で歯が外に押されて隙間ができる
- 上唇の真ん中にある「上唇小帯(じょうしんしょうたい)」というスジの位置が低く、歯の間に食い込んでいる
といったものです。
見た目の問題だけでなく、実はすきっ歯はお口の健康にも関わってきます。歯と歯の間に隙間があると、食べ物が詰まりやすくなったり、歯ぐきに炎症が起きやすくなったりすることがあります。また、噛む力のバランスが偏って、他の歯や顎に負担がかかる場合もあるんです。
ここで「マウスピース矯正」が力を発揮します。
軽度から中等度のすきっ歯であれば、透明なマウスピースを段階的に交換しながら、少しずつ歯を正しい位置に動かしていくことで改善が期待できます。例えば、前歯の間に2〜3ミリ程度の隙間があるケースなら、マウスピース矯正で十分対応できることが多いです。治療の過程では、必要に応じて「アタッチメント」と呼ばれる小さな樹脂の突起を歯に付け、マウスピースが効率よく力を伝えられるよう工夫します。
ただし注意点もあります。隙間が大きすぎる場合や、歯の欠損が関係している場合は、マウスピース矯正だけでは難しいこともあります。その場合は、部分的に補綴治療(セラミックやブリッジなど)を組み合わせることも検討します。つまり「すきっ歯=必ず矯正だけで解決」とは限らないんですね。
すきっ歯は「ちょっと可愛いチャームポイント」と思う方もいれば、「人前で笑うのが気になる」とコンプレックスに感じる方もいます。どちらにしても、その背景には歯や顎の大きさ、クセや生活習慣など、さまざまな要因が関わっていることを知っていただけると安心だと思います。
出っ歯(上顎前突)2.5mmまでの遠心移動が可能なケース
「出っ歯」と聞くと、多くの方が「前歯が前に出ている状態」というイメージを持たれると思います。専門的には「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」と呼ばれ、上の前歯、あるいは上顎そのものが前に突出している歯並びを指します。
この状態にはいくつかの原因があります。
- 歯の傾き:本来は垂直に並ぶはずの前歯が、唇側に傾いているケース。
- 顎の骨格の問題:上顎の成長が大きい、もしくは下顎の成長が小さいことで上下のバランスが崩れているケース。
- 生活習慣やクセ:指しゃぶりや舌で前歯を押すクセ、口呼吸なども原因になり得ます。
特に軽度~中等度の出っ歯では、「歯の傾き」が大きく関わっていることが多いです。つまり骨格的なズレが大きいわけではなく、歯そのものの位置や角度が原因になっているケースですね。
このようなタイプは、マウスピース矯正で改善できる可能性が高いです。透明なマウスピースを段階的に交換していくことで、前歯を少しずつ内側へ動かし、自然な位置に整えていきます。治療の際には、歯を効率的に動かすために「アタッチメント」と呼ばれる小さな突起を装着したり、必要に応じて歯と歯の間をほんの少し削る「IPR(ディスキング)」という処置を取り入れたり、親知らずがあれば後ろに下げるスペースを確保するため抜歯をすることもあります。これらにより、歯が前後に動くためのスペースを確保し、よりスムーズに並べられるようになるんです。
また、出っ歯は見た目だけでなく、実は機能面でも注意が必要です。前歯が前に出ていると、唇を閉じにくくなり、口呼吸の習慣につながりやすいんですね。口呼吸が続くと口の中が乾燥し、むし歯や歯周病のリスクが高まるほか、将来的にお子さんの場合はお顔の発育や姿勢にも影響が出ることがあります。
軽度〜中等度の出っ歯なら、マウスピース矯正は見た目の改善だけでなく、こうした機能的な問題の予防にもつながります。特に「人前で笑うと歯が気になる」「横顔の印象を少しでも整えたい」という方には大きなメリットになるでしょう。
ただし注意点として、骨格的に上顎と下顎の差が大きい「重度の上顎前突」の場合は、マウスピースだけでは限界があります。そのようなケースではワイヤー矯正や外科的な治療を併用することも検討します。ですので「自分の出っ歯はどの程度なのか」「マウスピースで対応できるのか」をしっかり診断してもらうことが大切です。
出っ歯は「見た目のコンプレックス」になりやすい一方で、口腔機能や健康面にも密接に関わる歯並びのひとつです。マウスピース矯正は、目立たず日常生活に馴染みやすい方法として、軽度〜中等度のケースにとても適しています。
軽度の反対咬合(受け口) ― 歯の位置が原因のケースについて
「受け口」と呼ばれる反対咬合(はんたいこうごう)は、下の歯が上の歯より前に出てしまう噛み合わせのことです。多くの方が「骨格の問題なのかな?」と思われるのですが、実はそうとは限りません。反対咬合のすべてが顎の成長や骨格的なズレによるものではなく、歯の生える位置や傾きによって起こるケースも少なくないんです。
たとえば、本来であれば上の前歯が軽く下の前歯にかぶさるように並ぶのが正常ですが、もし上の前歯が内側に傾いて生えてしまったり、逆に下の前歯が外側に傾いて生えてしまった場合、上下の前歯の関係が逆転してしまいます。これが「歯の位置が原因の反対咬合」です。
このタイプは、骨格的な問題が大きい場合に比べて比較的コントロールしやすく、マウスピース矯正で改善できる可能性が高いといえます。透明なマウスピースを段階的に交換していくことで、前歯の角度や位置を少しずつ理想的な方向に動かしていくのです。特に軽度であれば、歯を削るような大きな処置をせずに済むことも多く、見た目だけでなく噛み合わせそのものを自然に整えることができます。
ただし、実際の治療ではいくつか工夫が必要です。歯を前後に動かすためのスペースを確保するために、「IPR(アイピーアール)」といって歯の側面をわずかに削って隙間を作ることがあります。また、マウスピース単独では動きにくい方向への移動をサポートするために、歯の表面に「アタッチメント」と呼ばれる小さな樹脂の突起をつけることもあります。これらは見た目に大きく影響せず、ほとんどの方が日常生活で気にならない程度のものです。
反対咬合を放置してしまうと、前歯で食べ物をかみ切るのが難しかったり、発音に影響が出たりすることもあります。さらに、奥歯にかかる負担のバランスが崩れるため、長い目で見ると歯や顎関節に悪影響を及ぼす可能性もあるんです。「ちょっと下の歯が出ているかな…?」と気づいた段階で対処できれば、将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。
もちろん、骨格的に下顎が大きく前に出ているような重度のケースでは、マウスピース矯正だけでは難しいこともあります。その場合はワイヤー矯正や外科的な治療を組み合わせる必要があります。でも、「骨格の問題なのか、歯の位置の問題なのか」は自分では判断がつきにくいもの。だからこそ、歯科医院でしっかり診断してもらうことが大切なんですね。
軽度の歯の位置による反対咬合は、見た目の改善はもちろん、機能的にも大きなメリットがあります。マウスピース矯正は透明で目立ちにくいため、日常生活に取り入れやすく、ストレスが少ない治療法です。もし「子どもが受け口っぽい気がする」「自分の前歯が少し下に出ている」と思ったら、早めに相談することでよりシンプルな治療で済むかもしれません。
開咬(かいこう)
「開咬(かいこう)」とは、奥歯はしっかり噛んでいるのに、前歯の間にすき間ができてしまう噛み合わせのことです。鏡で見たときに「上下の前歯が触れない」「前歯で食べ物を噛み切りにくい」と感じたことがある方は、この開咬にあたるかもしれません。
開咬の厄介なところは、見た目だけでなく日常生活にも影響を与える点です。例えば、前歯が合わないせいでサンドイッチや麺類を前歯で噛み切るのが難しかったり、発音が不明瞭になることがあります。また、前歯で噛めない分、奥歯に大きな負担がかかるため、知らないうちに歯の摩耗や顎関節のトラブルを招いてしまうこともあるんです。
原因は大きく2つに分けられます。
ひとつは「骨格的な要因」。顎の成長や形の影響で上下の骨の位置関係がずれているケースで、この場合はマウスピース矯正だけでは難しく、ワイヤー矯正や外科的治療が必要になることもあります。
もうひとつは「歯や習慣による要因」。舌を前に押し出すクセ(舌突出癖)や口呼吸、指しゃぶりの影響で前歯の位置がずれてしまうタイプです。この場合は骨格的な問題ほど重くないため、マウスピース矯正で改善できる可能性が高いといえます。
マウスピース矯正では、透明なアライナーを段階的に使い分け、前歯の角度や位置を少しずつ整えていきます。さらに必要に応じて「アタッチメント」と呼ばれる小さな突起を歯に付けてコントロールを強化したり、舌や口周りの筋肉を整えるために「MFT(口腔筋機能療法)」を併用することもあります。これは単に歯を動かすだけでなく、原因となる習慣も改善して再発を防ぐためにとても大切なんです。
軽度から中等度の開咬であれば、マウスピース矯正で十分に対応できることも多く、見た目の改善はもちろん、「前歯でしっかり噛める」「会話がしやすくなる」といった機能面のメリットも期待できます。
まとめ
ここまでご紹介したように、マウスピース矯正は「軽度~中等度の歯並びのズレ」に強い治療法です。大きな外科的処置や目立つ装置を使わずに、透明のマウスピースで自然に歯並びを整えていけるのは、大人の方にとっても大きな魅力だと思います。
特に「人に気づかれたくない」「できるだけ自然に治したい」という方にはピッタリの方法といえるでしょう。
ただし、すべての歯並びに万能というわけではありません。歯のズレが大きい場合や、骨格的な問題をともなうケースでは、マウスピース単独では難しいこともあります。
次回は「マウスピース矯正では治せない、もしくは不向きな歯並び」について、具体的にお話ししていきます。
カテゴリ
- 虫歯 (53)
- 歯周病 (38)
- 小児歯科 (17)
- 矯正歯科 (30)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (5)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (20)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (19)
- 小児矯正 (19)
- マウスピース矯正 (40)
- ワイヤー矯正 (29)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (31)
- デンタルエステ (42)
- デンタルIQ (118)
- スタッフブログ (115)
アーカイブ
- 2026年1月 (3)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (5)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)