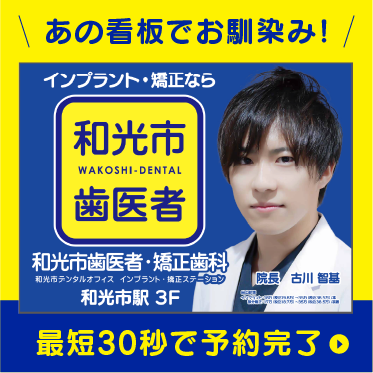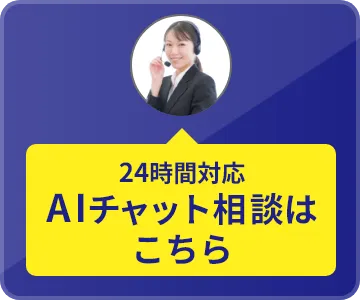和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
「毎日ちゃんと磨いてるのに…」すぐ虫歯ができる本当の理由とは?
患者さんからよくこんな言葉を聞きます。
「毎日しっかり歯を磨いてるのに、また虫歯ができちゃって…」
その気持ち、とてもよくわかります。私たちから見ても、ちゃんと磨けているように見える方ほど、
「なんで?」と思うような場所に虫歯ができてしまうことがあるんです。
でも、ここで覚えておいてほしいのは――
虫歯は“磨き残し”だけが原因じゃないということ。
お口の中の環境や食生活、唾液の力、そして歯の質や噛み合わせなど、
いくつもの要素が少しずつ重なって虫歯は進行していきます。
つまり、「磨いてるのに虫歯になる」には、ちゃんと理由があるんです。
この記事では、そんな“見えない虫歯の原因”を歯科衛生士の目線で、
専門的なことも交えながら、わかりやすくお話ししていきます😊✨
🦷虫歯ができるメカニズム

虫歯って、どうしてできるんでしょうか?
甘いものをたくさん食べると虫歯になる、って思ってる人が多いみたいだけど、実はもうちょっと複雑なんです。口の中で起こる化学反応が関係してるんですよ。
虫歯は、細菌、糖分、歯の質、時間、この4つがそろった時に進みます。食事やおやつを食べると、口の中にいる虫歯菌が糖分をエサにして酸を作ります。この酸が歯の表面をじわじわ溶かすんです。これが「脱灰」って言われる現象です。
でも、私たちの体ってすごいんですよ。唾液にはカルシウムとかリンみたいなミネラルが入ってて、溶けかけた歯の表面を元に戻す「再石灰化」っていう働きがあるんです。つまり、口の中ではいつも“溶ける”と“修復する”の戦いが起きてるんですね。
問題は、このバランスが崩れた時。
- だらだら食べたり、間食が多かったり
- 唾液が少ない→口呼吸だったり、ストレスがあったり、薬のせいだったり
- 歯垢がちゃんと落とせてなかったり
こういう状態が続くと、口の中が酸性になっちゃって、再石灰化が間に合わなくなるんです。その結果、歯の表面が白く濁り初期虫歯になり、そのうち黒くなって穴が開いちゃうんです。
急にできたように見える虫歯も、実は時間をかけてゆっくり進んでることがほとんど。なので、痛みが出てからでは、穴が開いてからでは意外と遅いんです。痛くなる前に、穴が開く前に虫歯にならないようにしましょう。
虫歯の進み方は、歯の質・唾液の量・生活習慣・・・原因は人によって違います。ちゃんと歯を磨いてるつもりでも、虫歯になりやすい人、なりにくい人がいるのは、そのためなんですね。
磨いてるのに虫歯ができる人の特徴

「ちゃんと磨いているのに、また虫歯…」ってよく聞きますよね。
毎日丁寧に歯磨きしてるのに虫歯ができると、「磨き方が悪いのかな?」って思いますよね。
でも、虫歯の原因って、磨き方だけじゃないんですよ。環境とか、生活習慣も結構大事なんです!
🧬① 唾液の力が弱まっている
虫歯を防ぐうえで、唾液の働きはとても大切です。
唾液には「洗い流す」「中和する」「再石灰化を助ける」という3つの力があります。
でも、ストレスや口呼吸、薬の副作用などで唾液が減ってしまうと、
お口の中が酸性に傾きやすくなり、虫歯菌が活動しやすい環境に。
特にデスクワークが多い方や、寝ているときに口が開いている方は要注意⚠️
「朝起きたときに口の中がカラカラ」「ねばつく」なんて感じる方は、
知らず知らずのうちに“唾液バリア”が弱まっているサインかもしれません。
🍭② 間食・飲み物のとり方に注意
「食べる量は多くないのに…」という方でも、
間食の“タイミング”や“回数”が多いと虫歯リスクはぐんと上がります。
例えば、仕事中にちょこちょこお菓子をつまんだり、
1日を通して甘いカフェラテやジュースを飲んでいたりすると、
お口の中は長時間“酸性状態”のままに。
虫歯菌は糖を食べて酸を出すので、
食べる・飲むたびにそのたびに歯が溶けかけてしまいます。
つまり、「だらだら飲み食べ」が一番危険なんです💦
③ 歯並びや詰め物の形が複雑で磨き残しやすい
歯並びが重なっていたり、過去に入れた詰め物や被せ物の段差があったりすると、
どうしても歯ブラシの毛先が届きにくい場所が出てきます。
特に歯と歯の間、奥歯の溝、詰め物の境目などはプラークが溜まりやすく、
そこから虫歯が再発してしまうケースも少なくありません。
実際、和光市デンタルオフィスでも
「しっかり磨けているのに、同じところに虫歯ができる」という方の多くが、
この“形態的な磨きにくさ”を抱えています。
そんなときは、歯間ブラシやフロスなどの補助器具を組み合わせることで、
しっかり予防につなげることができますよ✨
🌙④ 就寝前のケア不足
寝ている時は唾液があまり出なくなるので、口の中をきれいにする力が弱まるんです。
だから、もし汚れが残ったままだと、虫歯菌が夜通し頑張っちゃうことになるのです。
だからこそ、寝る前の歯磨きが一番大切!もし「朝と夜、どっちかをしっかり磨くとしたら?」と質問されたら、絶対に“夜”選ぶべきです🌙
☝️⑤ 歯の質や唾液の性質がもともと弱い
実は、歯そのものの強さや唾液の性質も個人差があります。
「エナメル質が薄い」「再石灰化が起こりにくい」など、
生まれつきの体質によって、虫歯になりやすい方もいます。
でもこれは「諦める」しかないわけではありません!
その分、定期的なクリーニングやフッ素ケアを取り入れることで、
しっかり虫歯を予防していくことができます🦷✨
⑥虫歯菌や酸を出す菌の多さ
虫歯は、ミュータンス菌やラクトバチラス菌といった細菌が原因で起こります。
実はこの菌の量や活動の強さにも、個人差があります。
🧫ミュータンス菌(Streptococcus mutans)
この菌は、虫歯の元凶とも言える存在です。
食べ物に含まれる糖分をエサにして酸を出し、歯を溶かしてしまうんです。しかも、ネバネバしたグルカンという物質を作って、歯にガッチリくっつくので、うがいだけではなかなか落ちません。
そのため、ミュータンス菌の繁殖が活発な人は、歯を磨いた直後はキレイでもあっという間に歯垢がネバネバになることが多いのです。つまり、この菌にとって快適な住みかになっているってことですね。
🧪ラクトバチラス菌(Lactobacillus)
こちらは、“虫歯の進行役”と呼ばれる菌です。
一度虫歯ができると、その中でこの菌がどんどん増えて、
深い部分まで酸を作って歯を溶かし続けるんです。
ラクトバチラス菌が多い人は、
「小さな虫歯が気づかないうちに進行していた」
「治療した歯がまた虫歯になった」
といった再発型のケースが多いです
✨まとめ
「きちんと歯を磨いているのに、なぜか虫歯になる…」
もしかしたら、磨き残し以外にも隠れた原因があるかもしれません。
虫歯菌の多さ、唾液の質、食生活、生活リズム、それに少しの噛み合わせのずれ。こういったことは、毎日の歯磨きだけでは気づきにくいものです。
でも、心配はいりません。口の中の状態は、原因を知ることで必ず変えられます。自分が虫歯になりやすい原因を見つけて、それに合ったケアを続ければ、「繰り返す虫歯」ともお別れできるでしょう。
私たち歯科医療従事者は、その”気づき”を一緒に見つけるお手伝いをします。一人ひとりのお口の状態をきちんと把握し、その人にぴったりのケアや予防方法をご提案します。
🌸次回予告
「磨いてるのに虫歯になる理由」がわかったところで、
次回はその“原因をどう防ぐか”に焦点をあててお話しします。
歯磨きの仕方を変えるだけではなく、
実は“唾液の力を引き出す工夫”や“食べ方の見直し”
“歯科でしかできない予防ケア”など、
虫歯を繰り返さないためにできることはたくさんあります。
次の記事では、歯科医療従事者の立場から、
「今日からできる虫歯予防のコツ」をわかりやすく解説していきます🩵
お口の中の小さな変化が、大きな違いを生みます。
そんな予防の力を、ぜひ一緒に感じてくださいね✨
カテゴリ
- 虫歯 (53)
- 歯周病 (38)
- 小児歯科 (17)
- 矯正歯科 (30)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (5)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (20)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (19)
- 小児矯正 (19)
- マウスピース矯正 (40)
- ワイヤー矯正 (29)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (31)
- デンタルエステ (42)
- デンタルIQ (119)
- スタッフブログ (116)
アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (5)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)