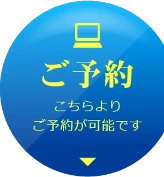和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
【歯ぎしり・食いしばり】様々な影響を及ぼす怖い習慣
こんにちは!
和光市デンタルオフィスです😊
突然ですが、皆さんにテストをします!
□頭痛持ちである
□歯のつめ物がよく取れる
□知覚過敏の症状が頻繁に起こりで冷たいものが歯にしみてしまう
□セラミックの被せ物が割れてしまった
□朝起きると、歯や顎に痛み・違和感がある
□顎のエラが張って顔が大きくみえる
□歯がすり減ってきた気がする
□歯茎が下がってきた気がする
さて、いくつあてはまりましたか??
2つ以上あてはまる方は、歯ぎしり・くいしばりを頻繁にしている可能性大です!!
【歯ぎしり・くいしばりって?】
「歯ぎしり」は、ギシギシと上下の歯をすり合わせること。
「くいしばり」は、上下の歯をぎゅーっと嚙みこむことをさします。
無自覚な方が多いのは、夜眠っている時なのどの無意識時に行っている場合が多いからです。
実はこの歯ぎしり・くいしばりは、ご自身の身体に大きく悪影響を及ぼす危険な行為です。
人間の噛む力は、ご自身の体重程度の力といわれています。
しかし、寝ているときなどの無意識下で歯ぎしりや、くいしばりをしている時にかかる力は、なんと1トン以上になるといわれており、恐ろしい力が歯にかかっているのが分かると思います。
そのような強大な力が、歯や顎に加わると、過度の負担となり、痛みの症状や歯が割れるといったトラブルにつながってしまうのも納得していただけると思います。
なので、歯ぎしりやくいしばりによる過度な負担から歯を守ってあげる必要があるのです。
【7割以上の人がしている歯ぎしり・くいしばり】
歯ぎしりやくいしばりをしていると気付いていない患者様は多くいらっしゃいます。
当院に通院していただいてる患者様の中にも、お口を拝見してみると、明らかに歯ぎしりやくいしばりをしている兆候が見受けられる患者様がた沢山いらっしゃいます。
歯ぎしりや食いしばりのご自覚があるか聞いてみると、皆さんご自覚がないようで、結構驚かれます。
無意識下での歯ぎしりやくいしばりは、成人の約7割以上が行っていると言われており、それを自覚して対処している人はやはり少ないように思います。
日々の生活で歯がダメになってしまう前に、なるべく早く症状に気付いて歯を守ってあげることが大切です。そのためにも定期検診は重要となってきます。
【実はおこさまにもある歯ぎしり・くいしばり】

こどもの歯ぎしりって大丈夫?
「子供が夜歯ぎしりしているみたいでギシギシ音がしてる・・・」
と、お子様の歯ぎしりを心配されたお母様から、よく相談を受けることがあります。
まだ6~12歳ぐらいのお子様が歯ぎしりをしていたら、顎にダメージがあったりなにか問題があるのでは?!と、とても心配になってしまいますよね。
ですが、お子様の歯ぎしりは殆ど心配することはありません。
6~12歳ぐらいの、混合歯列期の場合、どうしても歯が抜けたり生えてきたりで乳歯と永久歯と欠損部分で歯の噛み合せが悪くなってしまうので、歯ぎしりをすることで噛み合せのバランスを調整していると言われております。
なので、お子様が成長していく中で、歯ぎしりは必要なものなのです。
しかし、歯がたくさんすり減っていまったり、大人の歯が生えそろったあとでも歯ぎしりが続く場合は、治療が必要な可能性もありますので、定期検診での経過観察が必要です。
【歯ぎしり・くいしばりの種類3選】
一「歯ぎしり」「くいしばり」とよく一言で言いますが、実は大きく分けて3種類あります。
「グラインディング」「クレチング」「タッピング」です。
中でも歯や顎に大きく悪影響を与えてしまう傾向があるのが「グラインディング」と「クレンチング」この2つのタイプです。
特に「クレンチング」は歯への悪影響がとても大きく、最近、患者様の中でも増加傾向にある症状です。
◆グラインディング

ブラキシズムの種類
夜寝ている時の無意識下起こることが多いグラインディング。「歯ぎしり」というイメージと一致するのはこのタイプと言えます。
強く噛んだ状態で横にギシギシとこすり合わせるため、ひどい方だと音がするので、比較的周りの人に気が付いてもらいやすいです。
このグラインディングは、噛む面や歯の根元の「すり減り」が激しいのが特徴で、進行すると歯の表面のエナメル質という硬い組織が削れてしまい、象牙質という直接神経が繋がっている組織の部分が見えてしまうほどの人もいます。
歯がしみてしまう知覚過敏はこれが原因であることが多いです。
また、歯は上下の縦の力に対しては比較的強いと言われていますが、グラインディングによる歯が横に揺れる力には弱いため、歯を支える歯槽骨へのダメージはとても大きくなってしまいます。
これが進行すると、歯槽骨が吸収されてしまい、歯周病の悪化を助長させてしまう要因になります。
せっかく歯ブラシを頑張っていても歯周病になってしまうなんて、もったいないですよね。
~なぜグラインディングがおこるのか~
現代人のほとんどは夜寝ている間に歯ぎしりをしていると言われております。
人間が歯ぎしりをする大きな原因の一つとしてストレスがあげられます。
動物にとってなにかを噛むという行為は、そもそも相手を攻撃する行為ですよね。
自分が攻撃されるかもしれない敵に遭遇するという大きなの不安がストレスとなり、攻撃的に噛むという行動を発現することによって、ストレスを発散していると言われています。
私たち人間も、日々の生活の中で様々なストレスを受けていますが、現代人のほとんどがそのストレスを上手く発散させることが出来ないため、そのストレスは常に蓄積されていきます。
しかし、そういったストレスの蓄積は、人間の脳や体にとって重大な問題に繋がってしまうため、生命維持の防衛本能として、夜寝ている間にグラインディングをすることで溜まったストレスを発散しているのです。このグラインディングにより健康を維持しているとも考えられています。
◆クレンチング

ブラキシズムの種類
クレンチングとは、上下の歯をグッと強い力で噛みこむような行為で「くいしばり」や、「噛みしめ」と表現されることが多いです。
クレンチングの特徴は、夜寝ている間以外にも、昼間でも起こりやすいということです。
また、グラインディングと違ってほとんど音が出ませんので、ご家族の方や本人も、自分がクレンチングをしていると気付きにくいです。
クレンチングをしている人は、咬筋という頬の筋肉に力が入るためエラが張ってみえたり、口腔内に骨隆起と呼ばれる、骨のコブのようなものができたりします。
また、被せ物が割れやすいという方も、このクレンチング習慣がある方に多く見られます。
~本当に怖いのは噛んでいる時間の長さ~
本来、普段の生活のなかでリラックスしているときは、上下の歯は噛んでおらず、2ミリから3ミリ程度離れている状態が正常です。
上下の歯が接触する、いわゆる噛んでいる時間は、食事の時間を含めても、1日20分弱といわれています。
しかし、クレンチング癖がある人は、常にくいしばっている状態ですので、歯や歯茎、歯を支える骨などに大きな負担がかかってしまうのです。
こんな例があるのはご存じですか?
今、グーッと!思いっきり歯を食いしばってみてください。
何秒ぐらいくいしばり続けることができますか?
恐らく、5秒も続けられないと思います。
一般的には人間の噛む力は体重と同じぐらいといわれています。
なので、思いっきりくいしばった状態で5秒というと、仮に体重50kgの方の場合、歯にかかる力は
50kg×5秒=250kgです。
次に、噛む力を思いっきりくいしばった力を1/5ぐらいに落として、再び噛んでみてください。
これで何秒ぐらいくいしばり続けることができますか?
みなさん1分以上くいしばり続けることが出来るのではないでしょうか?
となると、その場合の歯にかかる力は、
10kg×60秒=600kg
となり、思いっきり噛んだ状態の時の力よりも倍以上の大きな力となります。
クレンチングのある方は、この状態を常日頃から無意識のうちに続けているので、歯・歯茎・歯を支える骨へのダメージがどれほど深刻なものなのかがお分かりいただけましたか?
◆タッピング

ブラキシズムの種類
タッピングとは、上下の歯をカチカチと噛む行為です。
寒くて震えるときなどカチカチとしますよね。
タッピングは歯や骨へに与える影響は、グランディングやクレンチングほど大きくはありません。
【歯ぎしり・くいしばりによって引き起こされる症状】
◆つめものが取れたり欠けやすくなる。
長時間歯に強い力がかかることで、歯と詰め物の間にある接着剤が少しずつ剝がれてしまい、外れてしまうことがあります。
詰め物が取れてしまう原因は、接着が十分に出来ていなかった場合や、詰め物の中がむし歯になってしまった場合なども考えられます。
しかし、取れてしまった詰め物の中がむし歯なっていないにもかかわらず、何度も頻繁に詰め物が取れてしまうような場合は、歯ぎしりが大きくかかわっていると言えます。
綺麗に取れた場合はそのまま再度詰めることもできますが、戻すことが難しいと判断された場合、歯を多めに削って治療し直しが必要になる可能性があります。
何度も治療しなおしたり、頻繁に歯医者さんに通わなくてはいけない状態は、患者様的にかなり負担になってしまいます。
◆知覚過敏がおこる
歯ぎしりにより強い力が加わると、歯の根元に応力が加わるため、歯の根元のエナメル質が削れ、くさび型に欠けた状態(くさび状欠損)になります。
くさび状欠損は、神経と直接つながっている象牙質が剥き出しになり、知覚過敏の症状が起きてしまいます。
応急処置としては、しみ止めの薬を塗ったり、プラスチックの材料で欠けた部分を埋めるという方法があります。
しかし、歯ぎしりの力でまた同じ場所に力が加わるとすぐに外れてしまうため、一時的な気休めになってしまいます。
最悪の場合、歯の神経が失活(死んでしまうこと)してしまうこともあります。
◆歯槽骨が解けて歯周病になる
歯ぎしりにより強い力が加わり歯が揺れると、歯周病の原因菌が歯周ポケット内に侵入し、歯槽骨が少しずつ溶けて、歯周病を助長させます。
歯周病の治療を行なったとしても、歯ぎしりによって歯槽骨が大きくなくなった状態では、なかなか完治するのは難しく、歯周病治療の一環として歯ぎしりの治療が必要になります。
◆神経の治療をした歯への影響
歯の神経の処置をした歯が痛みを感じるときは、根尖病変が再発するか、歯根膜炎である場合が多いです。
歯根膜炎とは、歯根の周りある歯槽骨と歯をつなげる膜(歯根膜)が炎症を起こすことです。
歯ぎしりやくいしばりで、歯や歯根に強い力が加わり、それが長く続くと、本来クッションの役割をしている歯根膜に負担がかかってしまいます。
よって歯根膜炎が起こり、歯茎の腫れや、歯が浮いたような違和感に繋がったり、噛んだ時に痛みを感じるようになります。
また、神経の治療をした歯は、歯に栄養がいかずにもろくなるため、歯の根が割れてしまう可能性があります。
そうなったら抜歯の対象になってしまうので、なにか違和感を感じたら早めに相談してください。
◆噛む筋肉への影響
噛む筋肉は、顔まわりにたくさんあります。
歯ぎしりやくいしばりにより筋肉が酷使されると、筋肉痛のような症状になり、頭痛・顎が疲れる・えらが張るなどの症状が起きます。
【和光市デンタルオフィスでの治療方法】
◆マウスピース(ナイトガード)

就寝用のマウスピース
当院では、歯ぎしりや食いしばりによる強い力から歯を守るために、就寝時に、歯ぎしり対策用のマウスピースを装着することをおススメしております。
歯ぎしり対策用のマウスピースには市販されてるものもありますが、使い方によっては、噛み合わせや歯並びを悪化させてしまう危険性もありますので、歯科医院にてご自身の歯にぴったり合ったものをお使いいただいたほうがベストです。
保険適用の範囲内で作成できますので、3割負担の方でしたら3000~4000円程度で作成することができます。
◆ボトックス治療

ボツリヌストキシン製剤注射療法
ボトックス(ボツリヌス)とは、ボツリヌストキシンと呼ばれる複合毒素から毒素を取り除かれて抽出されたタンパク質の一種です。
美容の世界ではシワ取りで使用されているので有名ですが、歯科では筋肉を弛緩させる作用があるため、歯ぎしり・食いしばりに有効な治療法です。
初回;2回分(100units)¥44000税込 1回分(50units)¥27500税込
リピート;2回分(100units)¥33000税込 1回分(50units)¥16500税込
◆オーラルマッサージ

顔の筋肉の緊張をほぐすマッサージ
歯ぎしり、食いしばりがある方は、顎や頬などお口周りの筋肉がとても緊張しています。
その筋肉の緊張が、頭痛や肩こりを引き起こしたりする場合もありますので、その筋肉の緊張を緩和させるためにお口の周りのマッサージをし、リラックスさせてあげることも有効です。
当医院では、アロマオイルを使用し、顔のむくみ・歪み・コリを改善するリラクゼーションマッサージを行います。
◆矯正治療

噛み合わせを治す矯正治療
歯並びによる噛み合わせの悪さは、歯ぎしりによるダメージをより悪化させます。
矯正治療はお口の中の環境を整える根本解決策として大切な選択肢の一つです。
嚙み合わせを治す矯正治療は医療費控除の対象にもなります。
当医院では、歯並びの無料相談を毎日実施しておりますので気軽にお問い合わせください。
いかがでしたか?
何気ない生活習慣でも、積み重なれば大きな障害となります。
この記事が少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。
カテゴリ
- 虫歯 (43)
- 歯周病 (27)
- 小児歯科 (11)
- 矯正歯科 (28)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (4)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (13)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (18)
- 小児矯正 (15)
- マウスピース矯正 (37)
- ワイヤー矯正 (28)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (28)
- デンタルエステ (37)
- デンタルIQ (110)
- スタッフブログ (105)
アーカイブ
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)