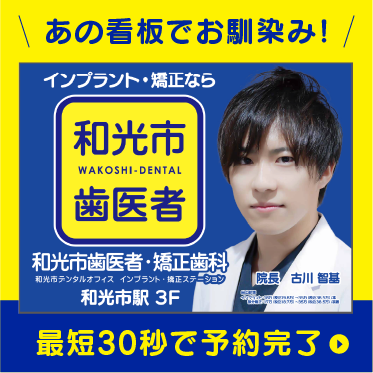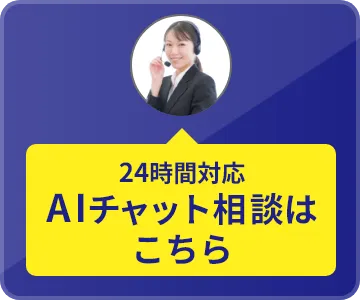和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
虫歯をつくらない習慣のつくり方―― “磨くだけじゃない” 本当の虫歯予防 ――
「ちゃんと磨いてるのに虫歯になる」――
そんな疑問の答えを、前回の記事では“原因”の視点からお話ししました🦷
虫歯菌のバランスや唾液の質、食生活、生活リズム…。
どれも日常の中で少しずつ積み重なって、虫歯のリスクを高めてしまうことがあります。
でも、裏を返せば――
その“日常”を少し見直すだけで、虫歯のリスクはグッと減らせるんです✨
今回の記事では、
「どうすれば虫歯ができにくいお口を育てられるのか?」
「どんな生活習慣が歯を守ってくれるのか?」
という、まさに“実践編”をお話ししていきます。
歯磨きのやり方を変えるよりも大切なのは、
自分の体とお口を理解しながら、虫歯になりにくい環境をつくること。
今日からできる小さな工夫を、歯科衛生士の視点でわかりやすくお伝えしますので、
ぜひ最後まで読んでくださいね。
唾液の力を引き出す生活習慣

— 唾液は“自然の修復液”です。これを味方につけると虫歯予防がぐっと楽になります —
まず大事なことを一言でいうと、唾液は「洗い流す」「酸を中和する」「再石灰化を助ける」という三つの大きな働きを持っています。だから唾液の量や質を整えることは、歯磨きだけでなく“体の状態を整える”ことそのものが虫歯予防につながる、ということなんです。
以下、仕組みの説明と具体的な生活習慣を一緒にお伝えします。
1)唾液の組成と働き(ちょっと専門的な基礎知識)
唾液って、水分だけじゃなくて、重炭酸とかリン酸塩、カルシウムも入ってるんですよ。これらが、酸でちょっと溶けちゃったエナメル質を元に戻してくれるんです。それに、リゾチームやラクトフェリンといった抗菌成分、IgAっていう免疫成分も入ってて、細菌が増えるのを抑える役割もしてくれるんです。だから、唾液の「酸を中和する力」と「分泌量」が多ければ多いほど、歯は酸に強いってことになりますね。
2)水分補給を習慣にする(まずはシンプルに)
口の中が乾くと唾液の“流れ”が落ち、細菌が留まりやすくなります。日中はこまめに水分を摂る習慣をつけましょう。特にデスクワークで長時間固まっていると唾液分泌が低下しやすいので、1時間に一回立ち上がって水を一口飲む、深呼吸をするなどで自律神経を整えるだけでも唾液が出やすくなります。寝る前は大量の水を飲む必要はありませんが、就寝中に口が渇きやすい人は枕元に水を置くのも一案です。
3)よく噛む習慣をつける(咀嚼刺激が最大の唾液刺激)
ガムでも食事でも、噛むこと自体が強力な唾液刺激になります。食後に「キシリトール含有のガム」を20分ほど噛むと唾液分泌が上がり、食後の口腔内pH回復を早めることが示されています。仕事の合間や外出先でのおやつ代わりに、甘味のないキシリトールガムを取り入れてみてください。ただしキシリトールは一日にまとめて大量ではなく、数回に分けて摂るのが一般的です。固い・繊維質の野菜、にんじんスティック、りんごなどをよく噛むのもおすすめです。
4)口呼吸・鼻づまりを改善する
口呼吸って、唾液がすぐ乾いて、口の中がいつもカラカラになる原因になるんですよね。もし、寝てるときにいびきをかいたり、鼻が詰まったりするようなら、耳鼻科で診てもらうのがおすすめです。アレルギーがないか調べたり、鼻の通りを良くしたり、アデノイドの状態を見てもらったり。家でできることとしては、寝る前に鼻うがいをしたり、加湿器を使って部屋の湿度を保つようにするといいですよ。
5)薬や持病の影響を把握する
抗ヒスタミン薬、抗うつ薬、降圧薬、利尿薬など多くの薬が唾液分泌を減らします。慢性的に口が乾く人は服薬歴を歯科医・歯科衛生士に伝えてください。場合によっては処方薬の変更を主治医と相談する、あるいは唾液代替品や唾液分泌促進薬の選択肢を検討します。
6)カフェイン・アルコール・喫煙は控えめに
カフェインやアルコール、喫煙は口腔乾燥を助長します。とくに就寝前のアルコールは一時的に口が渇きやすく、唾液の自浄機能を低下させます。可能なら量を減らす、飲み方を変えるなどの工夫を。
7)食べ方(回数と間隔)を工夫する
唾液が酸を中和して再石灰化を促すには休憩時間が必要です。間食や飲み物の回数が多いと、唾液が歯を修復する時間が取れません。日中は食事の回数を決め、間食は食後にまとめる、あるいはキシリトール製品にするなど酸にさらされる時間を短くする習慣を作りましょう。
8)就寝前の特別ケア
就寝中は唾液量が自然に減るため、夜のケアが決定的に大事です。就寝前の丁寧なブラッシング、フッ化物配合歯磨剤に加え、糖分のある飲食は避ける、必要なら唾液を補う、うがいでの清掃や人工唾液の利用などを行うと良いです。夜間に口が乾く方は、加湿器の使用も助けになります。
9)唾液の“質”を高める工夫(栄養と休息)
唾液の中の抗菌成分や緩衝能は栄養状態や睡眠にも影響されます。ビタミンA・C、タンパク質といった栄養が不足すると修復力が落ちますし、慢性的な睡眠不足は自律神経を乱して唾液分泌を低下させます。バランスの良い食事と規則的な睡眠は唾液力アップの基礎です。
10)専門的なサポート
歯医者さんでは、簡単な検査で唾液の量、質をチェックできます。その結果に合わせて、フッ素を塗ったり、歯のクリーニングをしたり、唾液が出やすくなるように生活習慣のアドバイスをしたり。必要であれば、人工唾液や薬の紹介もできます。もし、ずっと口が渇くとか、唾液が出にくいと感じるなら、自分で判断せずに、まずは相談してみてください。
最後に(実践しやすいチェックリスト風の短いまとめ)
・日中はこまめに水分補給を。甘い飲み物は避けましょう。
・食後20分は、キシリトール入りのシュガーレスガムを噛むのがおすすめです。外出先でも役立ちます。
・夜は寝る前にしっかり歯を磨き、寝る直前の飲食はやめましょう。
・口呼吸や鼻づまりが気になる場合は、耳鼻科に相談し、寝具や加湿環境も見直してみてください。
・薬を飲んでいたり、持病がある方は、歯科医に伝えて、自分に合った対策を相談しましょう。
唾液は、目に見えないけれど頼りになる存在です。日々のちょっとした工夫で、その力を引き出せます。今日からできることを少しずつ取り入れて、唾液の自然な力を活用しましょう!😊
食べ方の見直し(間食・飲み物の工夫)

— 「何を食べるか」よりも、「どう食べるか」で虫歯リスクは変わります! —
「甘いものを控えましょう」と言われると、ちょっと憂うつになりますよね。でも、実は“甘いものそのもの”よりも大切なのは、食べる回数とタイミングなんです。
虫歯は「食べた回数分だけ進行する」と言われるほど、口の中が酸性に傾いている時間がポイントになります。
🍭 どうして間食が多いと虫歯になるの?
私たちの口の中は、食事をすると一時的に酸性になります。これは食べ物の糖分をエサにした虫歯菌が酸を出すためで、その酸が歯の表面のカルシウムやリンを溶かしてしまいます。
でも唾液の力で、食後しばらくすると中性に戻り、再びミネラルが歯に戻る。この“脱灰と再石灰化のバランス”が保たれていれば、虫歯にはなりません。
ところが、ちょこちょこ食べ続けていると、この「回復する時間」がなくなってしまうんです。
お菓子やジュースをダラダラ摂ると、口の中は常に酸性状態=歯が溶け続けている状態に…。
つまり、“量より回数が大事”なんです!
☕ 飲み物も要注意!「無意識に酸性飲料を飲み続けていませんか?」
砂糖なしでも、酸っぱい飲み物には気をつけましょう。
例えば、
スポーツドリンク
炭酸水
フルーツジュース
これらは歯を溶かすので、よく飲むと歯の表面が弱くなります。水やお茶、砂糖なしの緑茶や麦茶は中性に近いので、口の中をきれいにする唾液の味方です。
ポイント!
・酸っぱい飲み物は、一気に飲んで口をすすぐのがおすすめですちょびちょび飲むのは良くないです。
・炭酸飲料やジュースの後は、水でうがいをするだけでも良いです。
・寝る前に甘い飲み物を飲むのはやめましょう。寝ている間は唾液が少ないので、酸が口の中に残ってしまいます。
🍰 間食の取り方を少し工夫するだけで虫歯リスクはぐっと下がる!
間食をゼロにするのは現実的ではありませんよね。
大切なのは、“まとめて摂る”意識です。
たとえば、お菓子を食べるなら「お茶の時間を決める」、食後のデザートとして楽しむのがおすすめです。
唾液が活発な食後に食べることで、酸の影響が少なくなります。
また、間食の内容も見直してみましょう。
◎ よく噛むもの、ナッツ・チーズ・ドライフルーツ少量など
◎ キシリトールガムやシュガーレスキャンディ
△ 砂糖入りのお菓子・ジュース・グミ・キャラメルなど粘着性の強いもの
特にチーズやナッツにはカルシウムやリンが含まれ、再石灰化を助ける働きもあります🧀✨
🍪 “食べた後のひと工夫”が虫歯を遠ざける
おやつの後や甘い飲み物を飲んだ後は、軽く水でうがいをする、またはガムを噛むだけでも違います。
これは「酸を洗い流してpHを戻す」効果があるからです。
歯磨きは30分ほど時間をおいてから行うと◎酸でやわらかくなったエナメル質をすぐ磨くと削れやすいためです。
☀️ “時間のリズム”を整えることも立派な予防法
意外かもしれませんが、夜更かしや不規則な食生活も虫歯リスクを高めます。
夜遅くに食べると、唾液が少ない時間帯に酸が長くとどまり、回復が追いつかなくなるためです。
規則正しい食事のリズムを整えることも、「唾液を味方にする」食べ方の基本なんです。
まとめ
甘いものが好きでも、食べ方やタイミングを少し工夫するだけで、虫歯のリスクはちゃんと下げられます。
「歯を守りたいから甘いものを我慢する」のではなく、「歯を守りながら楽しく食べる方法」を知ることが大切なんです。
和光市デンタルオフィスでは、あなたの生活習慣や食生活の癖も見ながら、「自分の歯を長く守る」お手伝いをしています。
「もしかしたら虫歯になりやすいかも?」と感じたら、気軽に相談してくださいね。
今日はここまで!また次回もお楽しみに!
カテゴリ
- 虫歯 (53)
- 歯周病 (38)
- 小児歯科 (17)
- 矯正歯科 (30)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (5)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (20)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (19)
- 小児矯正 (19)
- マウスピース矯正 (40)
- ワイヤー矯正 (29)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (31)
- デンタルエステ (42)
- デンタルIQ (119)
- スタッフブログ (116)
アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (5)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)