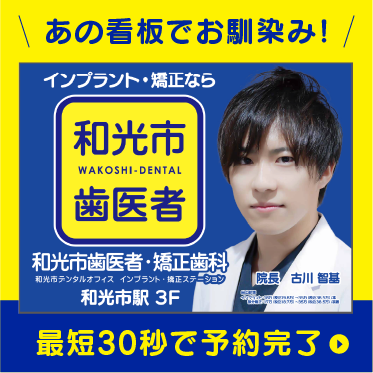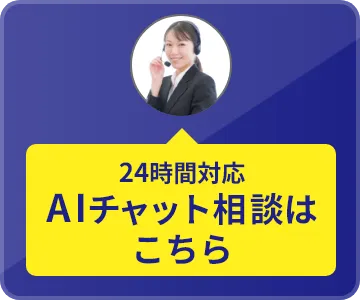和光市歯医者・矯正歯科|和光市デンタルオフィス
コラム・ブログ
COLUMN・BLOG
『育てる予防』のスタートライン—MFTと食育が子どもの歯並びを変える理由—part1
「うちの子、ちゃんと噛んでるのかな…?」
「口がぽかんと開いてることが多いけど大丈夫?」
最近、こんなご相談が本当に増えてきました。
実は今、“歯並びそのもの”よりも、その前段階である「お口の使い方」や「食べ方」が注目されていて、歯科の世界でも大きなテーマになっているんです。
というのも、昔は「歯並びって遺伝で決まるんでしょ?」と思われがちだったのですが、最新の研究では、
歯並びは“生活習慣”や“口腔機能の発達”に大きく左右される
ということがはっきりしてきました。
たとえば——
・舌の位置が低い
・口呼吸が多い
・丸飲みや早食いがクセになっている
・柔らかい食べ物中心で噛む回数が少ない
こうした“小さな習慣”が積み重なって、顎の成長や歯並びのスペース、姿勢、さらには集中力など全身へ影響していきます。
つまり、歯並びは「生まれつき」ではなく、「育つ環境」で大きく変わるもの。
ここで登場するのが、MFT 口腔筋機能療法、食育・食べ方・食材選び・噛む力の育て方
という2つの視点です。
MFTで“正しい口の使い方”を育て、
食育で“噛む力や顎の成長”をサポートする。
この2つは、どちらか片方だけでは不十分で、
セットで取り組むことで、はじめて子どもの歯並びや口腔機能が健やかに育っていきます。
今回はそんな“育てる予防”の第一歩として、
「なぜ今、MFTと食育が大事なのか?」
「どうして歯並びとそこまで関係しているのか?」
を、できるだけわかりやすくお話ししていきますね。
そもそもMFTとは? ― “お口の使い方を育てるトレーニング”

「MFTって最近よく聞くけど、実際なにをするの?」
そんな声がとても多いので、まずはここからお話しさせてください。
MFT 口腔筋機能療法とは、簡単に言えば お口まわりの筋肉の使い方を整えるトレーニング”のことです。
お口って、実は思っている以上にたくさんの筋肉が関わっていて、
・舌の動き
・唇を閉じる力
・頬の筋肉
・飲み込み方
・呼吸の仕方
がすべてリンクしています。
そして、このお口の使い方のクセは、歯並びやあごの成長に直結します。
なぜ「舌の位置」や「唇の力」が歯並びに関係するの?
これは少し専門的ですが、とても大事なポイントなのでやさしく説明しますね。
歯って、
舌 → 内側から押す力
唇と頬 → 外側から押す力
このバランスの中で、ちょうどいい位置に並ぶようになっています。
つまり、
✔ 舌がいつも低い位置にある
✔ 口がぽかんと開きやすい
✔ 指しゃぶりのクセが長く続く
✔ 飲み込みが「ベロを前に押し出す癖、幼児型嚥下」になっている
こんな状態が続くと、本来のバランスが崩れてしまい、
出っ歯・開咬・受け口・叢生デコボコなどの歯並びにつながることがあります。
実際、歯が動くのって“力がかかり続ける方向”なんですね。
だから舌がほんの少し前に押すクセがあるだけで、前歯はじわじわ押されて、数年後にはしっかり影響が出てしまうこともあります。
MFTでどんなことをするの?
よくあるのはこんなトレーニングです👇
・舌を上あごの正しい位置に置く練習
・唇を軽く閉じて鼻で呼吸する練習
・正しい飲み込み、大人の飲み込みの練習
・口の周りの筋肉をしっかり働かせる体操
・噛むリズムの改善
パッと聞くと「地味…」と思われるかもしれませんが(笑)、
これが実は“歯並びを育てるための土台づくり”としてとても大きな効果を持っています。
歯並びの悪化は、単に歯がガタガタだからではなく、
“お口の筋肉のバランスが崩れている結果”
というケースがすごく多いんです。
だから歯科では
「歯を動かすより先に、お口の使い方を整えよう」
という考えが主流になってきています。
小児だけじゃなく、大人にも効果がある?
実はあります!
もちろん成長期ほど劇的ではないですが、
・長年の口呼吸
・舌のクセ
・頬や唇の筋肉の弱さ
は大人になっても改善できます。
そして、MFTを取り入れることで
・矯正治療の安定が良くなる
・口呼吸が改善してだるさや乾燥が減る
・歯ぎしりの軽減につながる
など、嬉しい変化が現れる方もいます。
なぜ今「MFT × 食育」のセットが重要なの?
ここが今回のシリーズの肝なのですが、
MFTは“筋肉の使い方を整える”トレーニングで、
食育は“その筋肉を育てる環境づくり”。
たとえば、舌を正しく使う力が身についても、
・噛まない食生活
・丸飲みのクセ
・やわらかすぎる食事
が続いていたら、せっかくの成果が戻ってしまいます。
だからこそ、
「機能」MFTと「環境」食生活の両方を整えることが、子どもの歯並びを守る鍵になる
というわけです。
食育と歯並びの深い関係 ― “何をどう食べるか”でお口は育つ

MFTが「お口の使い方のトレーニング」だとしたら、
食育はそのトレーニングをほんものの力に変えるための、いわば筋トレの材料です。
よく保護者の方から、
「食事ってそんなに歯並びに関係あるんですか?」
と聞かれますが……実は、めちゃくちゃあります!
しかも、ただ“硬いものを食べればいい”という単純な話ではなく、
舌・頬・唇の筋肉が育つために必要な「食べ方のステップ」や「口の動き」があるんです。
一緒に深掘りしていきましょう。
食べ物の硬さだけじゃない。“噛む経験の質”が大切
よく「最近の食事は昔よりやわらかい」って言われますよね。
もちろんそれも理由の一つですけど、実はもっと色々なことが関係しています。
例えば、
- あまり噛まなくても食べられる、まとまった食品が多い
- とろとろ、ペースト状の食品が増えて、舌の動きが単調になりがち
- 離乳食を始めるタイミングが早すぎたり、遅すぎたりする
- おやつをよく食べるので、全体的に噛む回数が減る
こういった日々の積み重ねが、大きく影響しているんです。
つまり、何を食べるか と どう食べるか 、この2つがセットになって、お口の機能は育っていくんですね。
食育が歯並びに影響する理由
舌と頬をしっかり使える「飲み込み方」が育ちます。
やわらかすぎる食事ばかりが続くと、舌はほとんど動かなくなります。
舌で押し出して飲み込むような幼児型の飲み込みが続きやすくなります。
これ、成長期の歯並びにとても影響しやすいんです。
続くと…
・前歯が押されて出っ歯に
・奥歯しか当たらず開咬に
・嚥下時に頬筋が強く働きすぎて歯列が狭くなる
といった変化につながることがあります。
つまり、
食べるときに舌・唇・頬がバランスよく働いているか
これが歯並びの“土台”になります。
食育が歯並びに影響する理由②
意外と知られていませんが、
あごの骨は噛む刺 が入って大きく育ちます。
噛む回数が少ないと…
・あごが小さくなる
・歯の並ぶスペースが足りなくなる。叢生の原因
・舌の置き場が狭くなり、さらに機能が落ちる
といった負のループになりがちです。
逆に、
しっかり噛む経験が続くと、
・下あごが立体的に育つ
・頬骨〜口元のバランスが整いやすい
・呼吸が安定しやすくなる
など、全身の成長にも良い影響がでます。
噛むことって、歯並び以上に全身の成長に関わるような
実はそんなに大きなテーマなんです。
食育が歯並びに影響する理由③
呼吸・姿勢・集中力にもつながる
噛む刺激は、脳への刺激にもつながります。
「よく噛む子は集中力が続きやすい」と言われるのはそのため。
また、噛むためには
口が閉じていて、舌が正しい位置にあって、姿勢が安定していること
が必要なので、食育は口呼吸改善や姿勢の改善にもつながります。
つまり食育は、
“歯並びのためだけのものではなく、子どもの全身健康の土台”
といえるんですね。
食育 × MFTはセットで考えるべき理由
もしMFTだけやっても、
・いつも丸飲み
・噛まない食事
・とりあえず柔らかいものだけ
といった生活が続くと、
せっかく身についた口腔機能が維持できません。
逆に、食育だけやっていても
舌癖・口呼吸・飲み込みのクセが残ったままだと、
効果が半減してしまいます。
だからこそ、トレーニングMFT× 食生活食育を両輪で整える
このセットが今とても注目されているのです。
今日はここまで!次回もお楽しみに!
カテゴリ
- 虫歯 (53)
- 歯周病 (38)
- 小児歯科 (17)
- 矯正歯科 (30)
- 口腔外科 (12)
- 親知らず (5)
- 顎関節症 (9)
- 噛み合わせ異常 (20)
- マイクロエンド (5)
- セラミック (28)
- インプラント (19)
- 小児矯正 (19)
- マウスピース矯正 (40)
- ワイヤー矯正 (29)
- 部分矯正 (22)
- ホワイトニング (31)
- デンタルエステ (42)
- デンタルIQ (119)
- スタッフブログ (116)
アーカイブ
- 2026年1月 (4)
- 2025年12月 (4)
- 2025年11月 (5)
- 2025年10月 (4)
- 2025年9月 (4)
- 2025年8月 (5)
- 2025年7月 (4)
- 2025年6月 (5)
- 2025年5月 (4)
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (5)
- 2025年2月 (4)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (5)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (4)
- 2024年8月 (5)
- 2024年7月 (4)
- 2024年6月 (5)
- 2024年5月 (4)
- 2024年4月 (4)
- 2024年3月 (5)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (6)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (6)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (5)
- 2023年7月 (4)
- 2023年6月 (4)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (4)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (2)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年8月 (6)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (1)
- 2022年5月 (5)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (12)
- 2021年8月 (1)